[八経ヶ岳登山レポ]
11月に登る近畿地方最高峰の八経ヶ岳登山!大峰山縦走登山その1
観音峰登山口 ~ カナビキ尾根 ~ 明星ヶ岳 ~ 八経ヶ岳 ~ 弥山 ~ 行者還避難小屋 まで
- 大峰山(おおみねさん)日本百名山
- 大峰山は大和アルプスの異名をもつ、北は奈良県吉野から南は和歌山県の熊野まで、紀伊山地の中央を南北にのびる全長50Kmほどの山脈。 大峰山とは、広義には大峰山脈を指すが、狭義には山上ヶ岳をさす。しかし、山上ヶ岳は日本三百名山に、南部にある釈迦ヶ岳は日本二百名山に選定されているため、日本百名山の大峰山に登る場合、八経ヶ岳に登る登山者が多い。本サイトでは「日本百名山」の大峰山は、大峰山北部(八経ヶ岳以北)を日本百名山として捉え、北部の大峰山を形成する代表的な山、大普賢岳、稲村ヶ岳も百名山の扱いとしている。
- 八経ヶ岳(はっきょうがたけ)
- 大峰山脈の主峰で、奈良県および近畿地方の最高峰。標高は1,915m。
- 弥山(みせん)
- 大峰山脈を形成する一峰で、八経ヶ岳の北に位置する山。標高は1,895m。山頂近くに弥山小屋、山頂には弥山神社が鎮座している。
- 明星ヶ岳(みょうじょうがたけ)
- 大峰山脈を形成する一峰で、八経ヶ岳の南に位置する山。標高は1,894m。
- 大峯奥駈道(おおみねおくがけみち)
- 吉野と熊野を結ぶ大峯山を縦走する、修験道の修行の道。国の史跡「大峯奥駈道」として指定され、ユネスコの世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の一部でもある。古来より、大峯山寺より奥の「靡(なびき)」に進むことを奥駈と云われていた。修行場は「靡」と呼ばれ、ひとつひとつに番号が割り当てられている。熊野本宮大社の本宮大社の第一行所(靡)にはじまり、吉野川河岸の柳の宿の第七十五行所(靡)に終わる。
大峰山 八経ヶ岳のコース
なお、縦走であれば、南の釈迦ヶ岳や北東の行者還岳から縦走してくることも可能。また、下記以外に、西の天川和田から登るコースもあるが、コース距離も長く、コースも難路指定されているので割愛している。
- 双門コース登り利用
北の観音峰登山口からの登るコース。なお、詳細にはこのコースでも3パターンほど存在する。
【カナビキ尾根 + 明星ヶ岳】
観音峰登山口 ~ みたらい渓谷 ~ 熊渡 ~ 金引橋 ~ ナベの耳 ~ 日裏山 ~ 明星ヶ岳 ~ 八経ヶ岳【カナビキ尾根 + 弥山】
【弥山川 + 弥山】
観音峰登山口 ~ みたらい渓谷 ~ 熊渡 ~ 金引橋 ~ ナベの耳 ~ 狼平避難小屋 ~ 弥山 ~ 八経ヶ岳
観音峰登山口 ~ みたらい渓谷 ~ 熊渡 ~ 仙人嵓前のテラス ~ 狼平避難小屋 ~ 弥山 ~ 八経ヶ岳
- 行者還コース下り利用人気コース!
- 西の行者還トンネル西口からの登るコース。コース距離も短く最も利用者が多い。
なお、行者還トンネル東口から一ノ垰(いちのたお)を経由しても登れるが、行者還トンネル東口には駐車場がない上、 無駄にコース距離が長くなるため、殆どの登山者は行者還トンネル西口を利用してる。
- 天川コース
- 北西の天川川合から門前山や栃尾辻を経由して登るコース。
なお、詳細にはこのコースも双門コース同様に、狼平避難小屋・弥山を経由するコースと、日裏山・明星ヶ岳を経由するコースとがある。
大峰山縦走登山の計画
- プラン
- たまたま、仕事の関西出張と11月の3連休が重なったため、計画。3連休の天候は21日は晴れ、22日は晴れのち曇り、23日は雨。そのため、21日初日のスケジュールを長めにとり、23日は下山するだけの予定を立てた。
- コース
- 大峰山を縦走する場合、時計回りに縦走するのが一般的。深田久弥氏も洞川から時計回りに縦走している。問題となったのは、弥山小屋が今シーズンの営業を終了しており、山上ヶ岳の大峯山寺も9月で閉鎖されているため、宿坊も利用できないこと。宿泊施設で候補となるのが、稲村ヶ岳山荘(12時の方角)、小笹宿(1時の方角)、行者還避難小屋(3時の方角)、狼平避難小屋(7時の方角)。小笹宿は小屋が小さいため、万が一を考えテントがないと厳しいため却下。初日のスケジュールを長めで3日は短めという前提を考慮して、決めたのは反時計回りの縦走。しかし、初日は移動距離が長く、11月の登山としてはカツカツのスケジュールで挑むことになってしまった。
関連レポート
八経ヶ岳コースレポート
観音峰登山口 ~ 双門コース分岐
前日の仕事が押してしまったため、観音峰登山口の駐車場に到着したのは、予定より2時間遅い深夜の3時半。車内で1時間ほど仮眠をとるが、寝たのか寝てないのかわからない眠りの浅さ。
なお、駐車場には4台の車が駐車している。皆、車中で睡眠をとっているようだが、男女ペアの登山者は休憩所の中にテントを張っていた。
【4:59】観音峰登山口を出発。
ギリギリまでアイゼンを持参するか迷っていたため、男女ペアの登山者にアイゼンの有無を尋ねたところ、「持ってきていない」とのことだったので、自分も車中に置いて出発。結果的にアイゼンは全く必要なかったので、持っていかないのが正解だった。
白倉谷、川合と書かれた道標。白倉谷方面にはロープが張られている。この道標から、真逆に進んでいる可能性はなくなったが、この分岐も少し戸惑う。白倉谷と白倉出合って似てるけど、さすがにロープ張ってあるので違うと判断し、右側に曲がりみたらい渓谷に向かう。
みたらい渓谷に到着後は、熊渡に向かって林道歩き。時間は6時で周辺はまだ真っ暗だが、林道を歩いていると何故か車がよく通る。【5:54】熊渡に到着。
橋を渡ると、一般通行禁止の注意書き板。この注意書きにも戸惑う。仕方なく、今回持参した登山用GPSで確認すると、間違いなくココが熊渡と判明。一般通行禁止を無視して少し進むと、登山ポストを発見しホッと一安心。それにしても、一般通行禁止とか紛らわしい注意書きはやめてほしい。
 双門コースの分岐地点に到着。
双門コースの分岐地点に到着。
どちらに進んでも八経ヶ岳に到達できるが、左は弥山川沿いを進む超難コース。さすがに今回はパスして、右側のカナビキ尾根から登る。なお、このカナビキ尾根も山と高原地図では破線表示される難コース。
双門コース分岐 ~ カナビキ尾根分岐
【6:37】双門コースの分岐地点を出発。
金引橋の側に水場があり、今回は弥山小屋も営業終了、狼平避難小屋にも寄らないので、本日最後の水場。最終目的地の、行者還避難小屋まで水は手に入らない。
 ようやくカナビキ尾根を登り切る。この地点で、天川コースと合流。※写真は進行方向とは逆の天川川合方面
ようやくカナビキ尾根を登り切る。この地点で、天川コースと合流。※写真は進行方向とは逆の天川川合方面
結局、カナビキ尾根を登り切るのに2時間かかる。この登りはめちゃくちゃしんどかった。登山好きじゃなければ、決して登りたくない辛い上り。今回の大峰山縦走で、体力的に最も厳しかったのは、このカナビキ尾根。到着後は、疲れでコースに倒れこむ。ちなみにここまでの区間、登山者には1人も会っていない。
カナビキ尾根分岐 ~ 高崎横手出合
 地名標識はなかったが、地形的に頂仙岳手前の鞍部なのでこの地点がナベの耳の筈。(振り返って撮影)
地名標識はなかったが、地形的に頂仙岳手前の鞍部なのでこの地点がナベの耳の筈。(振り返って撮影)
【9:07】ナベの耳を通過。
上記写真の平坦で広がっている地点がナベの耳。後に写真撮影時間とGPSの軽度・緯度から調べても、合致していたので間違いないと思う。地名標識は見当たらなかった。
 高崎横手出合に到着。
高崎横手出合に到着。
疲れたので少し中休憩。ココからは、日裏山経由、明星ヶ岳の北側をかすめて八経ヶ岳を目指す。
高崎横手出合 ~ 八経ヶ岳
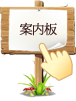
高崎横手出合から日裏山までは、苔の森が広がっている。案内板にはシラビソやトウヒの幼木を踏まないように、注意喚起されているが、出発直後いきなり道に迷う。すぐにコースに戻ることはできたが、植生保護の観点からも、道はわかりやすくしておいて欲しい。
日裏山まで近づくにつれ、要所で見晴らしの良い場所が出始める。
日裏山周辺は、景色が開けている。これまでずーと展望のきかない樹林帯が続いていたので、この日初の展望にテンションが上る。
写真撮影だけして直ぐに出発。次なる目的地は弥山辻。
 日裏山からの展望。
日裏山からの展望。
 日裏山の山頂周辺。
日裏山の山頂周辺。
 弥山辻に到着。
弥山辻に到着。
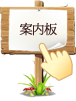
【10:47】弥山辻に到着。
明星ヶ岳は弥山辻から南に少し進んだ場所にあり、第五十番目の行所。行くべきか、行かないべきか迷っていると、たまたま明星ヶ岳の方からやってきた登山者と遭遇。明星ヶ岳の事を聞いてみると、弥山辻から明星ヶ岳まで数分で山頂標識もあったとのこと。それを聞きザックをデポして、明星ヶ岳を目指す。
ココから八経ヶ岳の山頂までは約20分。
 八経ヶ岳山頂に到着。
八経ヶ岳山頂に到着。
【11:18】八経ヶ岳山頂に到着。
岳は第五十一番目の行所で、以降大峯奥駈道でたまに見かけるようになるが、遊行僧が携帯する杖、錫杖(しゃくじょう)が刺さっている。
これまで殆ど見かけなかった登山者だが、八経ヶ岳の山頂は登山者多数。一体どこから出現したのかと思いきや、殆どの登山者が行者還トンネル西口から登ってきているようだ。空手の登山者も多く、そういった登山者は弥山小屋にザックをデポしている。山頂スペースは広くないが、20人ほどの人数に対してギリギリ許容範囲内。昼時なのに、食事をしている人が殆どいないのは、多くの登山者は弥山小屋で食事をしているため。既に弥山小屋は営業を終了し、水の調達やトイレの利用などはできないので、弥山小屋にこだわる必要はないと思うが、ベンチの有無や八経ヶ岳の山頂スペースの狭さなどから暗黙の了解なのかな。
八経ヶ岳山頂からの展望は、北側以外が開けている。展望は良好だが、関東のように富士山や北アルプスなど特徴的な山々がないため、コレといったビューポイントがないのは残念。同じ百名山の大台ヶ原山も地味な感じだったし。 北東方面。正面が弥山で小さい建物が弥山小屋。
北東方面。正面が弥山で小さい建物が弥山小屋。
 八経ヶ岳山頂から東側。矢印のあたりが、同じ百名山の大台ヶ原山。
八経ヶ岳山頂から東側。矢印のあたりが、同じ百名山の大台ヶ原山。
 南西方面。正面の山が明星ヶ岳。手前に伸びるのが歩いてきた稜線。
南西方面。正面の山が明星ヶ岳。手前に伸びるのが歩いてきた稜線。
八経ヶ岳 ~ 弥山小屋
【11:45】弥山小屋へ向けて出発。
当初、八経ヶ岳山頂で昼食予定だったが空気を読んで、弥山小屋で食べることにした。腹ペコだが、弥山小屋まで20分ほどなのでそれぐらいは我慢できる。
 弥山小屋へに到着。
弥山小屋へに到着。
【12:22】弥山小屋へに到着。
弥山は第五十四番目の行所。空腹で八経ヶ岳を出発し、途中の道迷いで焦り必死に八経ヶ岳まで戻ったため、弥山小屋に着いたときはもうクタクタ。兎にも角にも、まずは腹ごしらえ。
弥山小屋は収容人数200名で、個室もある大きな山小屋。しかし、弥山小屋は営業を終了しているため、水の調達はおろかトイレも利用できない。今年は暖冬のためか、この季節にしては登山者も多いので、登山者としては、もう少し営業を延長して欲しいところだけど。
弥山小屋から弥山神社のある弥山山頂まで、5分ほどで到着できる。景色を楽しみながら食事をしたいなら、弥山小屋より弥山神社のある山頂付近で食事をすると良い。弥山 ~ 奥駈道出合
【13:15】弥山を出発。
次なる目的地、行者還トンネル西口との分岐地点である奥駈道出合(おくがけみちであい)。
 聖宝ノ宿跡。写真の像は理源大師像。
聖宝ノ宿跡。写真の像は理源大師像。
この聖宝ノ宿跡だが、大峯奥駈道の行所では、講婆世宿(こうばせのしゅく)となっている。この聖宝ノ宿跡に到着した時、正規の登山道ではない理源大師像(りげんだいしぞう)の後ろから出てきてしまう。どうやらコース外を歩いていたようだ。この行者還コースだが、コースが広がり踏み跡も広がっている箇所もあるため、意外と小さな道迷いが発生しやすい。まあ、遭難するようなレベルではないと思うが。
 奥駈道出合に到着。
奥駈道出合に到着。
周りを歩いていた登山者の全員が、行者還トンネル西口へ下っていく。まあ、想定はしていたが、日が暮れかけているので、余計寂しく感じる。
奥駈道出合 ~ 行者還避難小屋
その後の一ノ多和(地図には一ノ垰と記載)は第五十七番目の行所。なお、過去一ノ多和にあったボロボロの避難小屋は、2014年11月に撤去されている。
 行者還避難小屋に到着。
行者還避難小屋に到着。
【16:04】行者還避難小屋に到着。
さすがに前日殆ど寝ない状態で、約11時間の道のりを歩き抜くのは疲れた。
この日の行者還避難小屋利用者は、ソロ男性×3名、男女ペア×1組、シニア女性団体10名の合計14名。中央の吹き抜け部屋を同じソロの男性と2名で専有して使わせてもらう。同部屋のソロ男性とは、よく会話をしたが、他の登山者とは部屋が違うこともあり、あまり会話を交わす機会はなかった。なお、同部屋のソロ男性は、北の吉野からの縦走で、明日は天川川合に抜ける予定とのこと。多少コースは異なるが、いわゆる縦走の時計回りで自分とは逆回り。
前日殆ど寝ていなかったこともあり、19時頃には就寝。マットがなかったので、比較的ペタンコの毛布を下に敷き、その上でシュラフに包まり、シュラフの上から毛布を掛けて眠りについた。
To be continued...関連レポート
八経ヶ岳縦走のコースタイム
| 予定 | 実際 | 場所 |
|---|---|---|
| 05:00 | 04:59 | 観音峰登山口出発 |
| 06:00 | 05:54 | 熊渡 |
| - | 06:28~06:37 | 双門コースの分岐 |
| - | 08:24 | カナビキ尾根分岐 |
| 09:00 | 09:07 | ナベの耳 |
| - | 09:28 | 高崎横手出合 |
| 10:00 | 10:02 | 日裏山 |
| 11:10 | 10:47~11:05 | 弥山辻 |
| 11:30~12:30 | 11:18~11:45 | 八経ヶ岳 |
| 13:00 | 12:22~13:15 | 弥山 |
| 13:45 | 13:43 | 聖宝ノ宿跡 |
| 14:45 | 14:27 | 奥駈道出合 |
| 15:15 | 15:09 | 一ノ垰 |
| 16:30 | 16:04 | 行者還避難小屋 |
八経ヶ岳縦走の難易度

21/30
総合難易度| 必要体力 | |
| コース距離 | |
| 所要時間 | |
| 危険度 | |
| 登山難易度 | |
| 小屋・水場 | |
| アクセス | |
| 総合難易度 | |
登山DATE
- 歩行距離:22.85km
- 登山歩数:37,455歩
- 高度上昇:1,817m
- 高度下降:1,205m
- 出発高度:0,775m
- 最高高度:1,915m
- 標高の差:1,140m
- 活動時間:09:18
- 休憩時間:01:47
- 合計時間:11:05
お気軽にどうぞ!



 大普賢岳登山レポ行者還岳から縦走する大普賢岳登山!大峰山縦走その2
大普賢岳登山レポ行者還岳から縦走する大普賢岳登山!大峰山縦走その2 山上ヶ岳登山レポ女人禁制の山上ヶ岳登山!大峰山縦走登山その3
山上ヶ岳登山レポ女人禁制の山上ヶ岳登山!大峰山縦走登山その3 稲村ヶ岳登山レポ稲村ヶ岳・大日山から観音峰へ!大峰山縦走登山その4
稲村ヶ岳登山レポ稲村ヶ岳・大日山から観音峰へ!大峰山縦走登山その4




















































































初日に歩いたコースで危険箇所と言えば、カナビキ尾根がコース不明瞭なことによる道迷いぐらい。後に縦走する行者還岳、七曜岳、大普賢岳、山上ヶ岳と比べて、滑落するような危険箇所はない。
山小屋・水場の観点では、時期の問題で弥山小屋が営業していなかったのは痛かった。弥山小屋が営業していない場合の縦走は、水の確保の観点からも明星ヶ岳経由ではなく、狼平避難小屋を経由した方が安全。結果的に行者還避難小屋の水場が枯れていなかったので良かったが、時期によっては枯れるらしいので、万が一に備えリスクッジしながら計画を立てた方が良い。